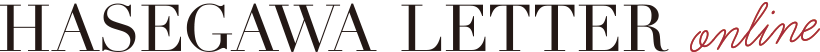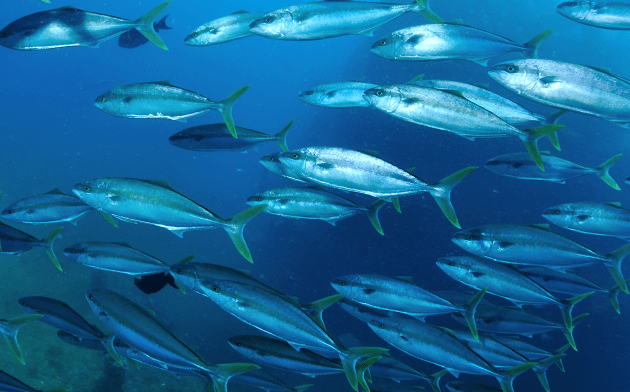HASEGAWA LETTER 2024 年( No.42 )/ 2024.03


社会の中の香り
植物をめぐる話 ~小石川植物園から見てきたこと~
はじめに、小石川植物園(正式名称:東京大学大学院理学系研究科附属植物園)について簡単にご紹介します。東京都文京区白山の地にあり1877(明治10)年に東京大学が設立されたことに伴い日本で初めての植物園として開園しました。面積は約16 haあり高低差のある地形を生かした園内には約7000本の樹木と千数百種の草本類、温室では千数百種の多様で希少な植物を見ることができます。広い敷地の中には、徳川第5代将軍綱吉ゆかりの日本庭園や自然湧水を生かした池やハナショウブ、ウメ、サクラ、薬園時代からの植物が見られます。東アジアの多様で豊かな植物を利用し東京大学での様々な研究と実験を行っています。大きな樹木が生い茂った植物園は都民の貴重な緑地となっています。小石川植物園で働きながら気がついた植物と香りの不思議な関係や自然保護や環境保全の事柄についてこの場をかりて話してみたいと思います。
植物好きの少年と小石川植物園との出会い
私は、1960年東京都品川区に生まれました。京浜工業地帯のはずれの町で育ちましたが、自宅周辺には緑地が多く、自宅の庭でも果樹や花木に囲まれた生活を送っていました。物心ついた1970年頃は、大都市の大気は光化学スモッグ(光化学反応による大気汚染)で汚れ、東京の空は灰色だったのを覚えています。海や川は汚れて濁っており、酸性雨で木が枯れるなど公害の報道に心を痛めていました。森林の樹⽊が汚れた空気をきれいにする働きがあると知ったのも同じ頃でした。
「公害で大切な緑が失われるならば増やせばよい」「森を守りきれいな空を取りもどす」と考えるようになり、私は東京都立園芸高校に興味を持ち、受験前の下見に世田谷区等々力の園芸高校に向かいました。学校に着くと、正門から真っすぐ続く黄色い立派なイチョウ並木が見えました。校内には西洋庭園や様々な樹木、都会にあるとは思えないほどの緑に囲まれていました。「ここに通いたい」学校の優れた環境が決め手となり、造園科に進学しました。
園芸高校造園科卒業後、1978年に東京大学理学部附属植物園(通称:小石川植物園)の文部技官として採用されました。当時の先輩職員たちは戦後からの復旧が大きな仕事で改修には長い時間がかかりましたが、私が就職した頃にはだいぶ落ち着いてきていました。それでも戦後各地から集めた植物が圃場(ほじょう:苗木を育てるために植える畑)で大きく育ち、その処理をどうするか、園内の植栽物の再構築が必要な時期でもありました。
私が就職した最初の1年間は、温室係の先輩について仕事を学びました。温室の植物の灌水(かんすい)、植え替え、ランの栽培など温室のすべての仕事を経験しました。2年目からは分類標本園整備の仕事が付加され、600種類の生きた標本(植物)の栽培方法を学びました。現場を担当した9年間で分類標本園の整備を終えると、次は樹木園係に異動しました。当時、樹木園係の主任の定年退職が迫っていたので、園内全体の植物管理ができるように引き継ぎを行いました。戦後に作られた園内の植栽図は目測で作られた大ざっぱなものでしたので、通常業務の合間に簡易測量しながら7年の歳月をかけて園内の植栽図を作成しました。園内管理には不可欠なものだと感じていたので、先輩の在職中に何とか間に合わせることができました。植栽図ができた後、植物を登録する「東京大学理学部附属植物園 植栽分布記載システム」(1997年)を構築し、パソコンで園内の樹木の掌握は誰でもできるような体制を作りました。
その間、自然災害などの被害復旧や植物の栽培を続けながら、樹木園係を30年間担当しました。2020年に定年を迎え、現在は再雇用職員として、次世代を担う技術職員に自分の技術・知識の伝承を行っております。
長年、小石川植物園にたずさわってきましたが、植物や樹木との付き合いは楽しいものです。そして不思議な生態や現象にわくわくします。本園で出会える植物を通して自然や環境についてお話しさせていただきます。

小石川植物園で体験する世界的な生物学の発見
古生代(約5億4100万~約2億5190万年前)に、水中に生活していた藻や原始的な植物は地上に進出し上陸すると、その環境に順応し地上で生活できるように進化を遂げます。厳しい生存競争を生き延びてきた種だけが、現在生き残っています。水中に生活していた植物が陸上に進出し始めた最初の過程では、シダの仲間は前葉体を作って地上の生活に順応し対応しました。
その次の世代では、植物体が胞子嚢を作り繁殖できるように変化し、その器官の一部が花に進化していったと考えられています。裸子植物のイチョウやソテツは生殖器に胞子嚢に似た形態を持っており、雄株と雌株に分かれ生殖を行う極めて原始的な植物です。
植物園の記念樹 大イチョウ
植物園では、4月の中旬頃にイチョウの雄花から空中に放たれた花粉が雌花の先から出る受粉滴に捕らえられ、若いギンナン(雌花の中で)の中に入り成熟が進み、8月の下旬頃ギンナンの体液の中を卵子まで泳ぎ受精が成立します。
1896(明治29)年、ギンナンの殻の中から精子を取り出して顕微鏡で観察し、精子が繊毛で泳ぐことを発見したのが、帝国大学理科大学植物学教室の助手をしていた平瀬作五郎です。平瀬は、帝国大学農科大学助教授の池野成一郎がソテツの受粉機構の研究をしていた時に、その手伝いでイチョウの研究をしていましたが、先に精子の発見に至りました。平瀬作五郎は池野成一郎の弟子にあたるのですが、世界初のイチョウの精子発見は平瀬の栄誉となりました。二人は研究者としてお互いを尊敬しており、東京帝国大学が研究を指導していた池野を帝国学士院恩賜賞に推薦しようとした時、池野は平瀬と一緒でなければ賞は受けないと主張し、二人一緒に受賞(1912年)したという美談も残っています。
この研究は、日本人の植物学者による世界的な発見で生物学上の偉業とされています。この実験に利用したギンナンを採集したのが、小石川植物園のほぼ中央にあるイチョウの木です。「精子発見のイチョウ」と呼ばれており、本園のシンボルツリーとなっています。


右下:イチョウの雄花 (2007年撮影)
植物園の記念樹 ソテツ
平瀬作五郎がイチョウの精子を発見したのち、池野成一郎も鹿児島県物産陳列場(現鹿児島県立博物館)から取り寄せたソテツで研究を進め、1896(明治29)年に、ソテツの精子を発見しています。
池野が鹿児島県立博物館でソテツの受粉機構の研究に使用したソテツから株分けして分譲(1983年)してもらった株を小石川植物園の正門近くに記念樹(1992年)として植栽して展示しています。



左下:大胞子葉とソテツの胚珠、右下:左からソテツの胚珠(種皮外層)、ソテツの胚珠(種皮中層)、イチョウのギンナン (2023 年11 月撮影)
植物のにおいと受粉戦略
私が、小石川植物園で一番感銘を受けたにおいは、バニラビーンズの香りです。ある日バックヤードの植物栽培用の温室に入ると、全体に甘い芳香が充満していました。驚いてそのにおいをたどってみると、バニラビーンズが蔓についたまま自然発酵して芳香を放っていました。バニラの蔓に花が咲いたことも気がつかなかったので本当に驚きました。
翌年にバニラの花も確認しましたが、緑色の地味なランの花で蔓やバニラビーンズの緑色と完全に同化していて、においもなく本当にひそやかに咲いていました。商業的にバニラは人工授粉が必要で、バニラビーンズはキュアリングという加工工程を経て利用されていますが、偶然が重なって自然受粉、発酵して奇跡の芳香が得られたのだと思います。


生物を惹きつけるのはいい香り? 不快な臭い?
いい香りを創り出す植物の戦略的な意図は、その種子や花粉を昆虫などに運んでもらうためだと考えられています。一般的に昆虫は甘いにおいのするものや蜜を運んで蓄える性質があります。実がなるものはそれを鳥などに食べてもらい糞として他の土地に運ばせる繁殖戦略を取っています。鳥は昆虫に比べ行動範囲が広いので、生育範囲を広げることが可能になります。
いい香り、悪い臭いとはあくまで人間の主観です。人間にとっては不快な臭いでも花粉を運ぶ手伝いをする生物を惹きつける香りを出す植物もあります。
小石川植物園での不快な臭いを出す代表は、世界で一番大きな花序を持つといわれるショクダイオオコンニャクAmorphophallus titanum(タイタン:ギリシャ神話に登場する神。巨神族)、そして一番背が高い花序を持つといわれるAmorphophallus gigas(ギガス:ギリシャ神話の巨人)です。これらはコンニャクの仲間で種をまいてから花が咲くまでに十数年を要し、塊茎(コンニャクイモ)の重さは数十キロに達します。どちらの種もインドネシアのスマトラ島にだけ分布する希少種で、絶滅危惧種になっています。小石川植物園では1991年から温室で栽培しており、数十年前からは繁殖に取り組み、増えた株は日本各地の植物園に分譲しています。


不快な臭いの植物 ショクダイオオコンニャク
本園のショクダイオオコンニャクは、1991年に池袋の東武百貨店で行われた「世界の貴重な植物展」で展示された塊茎を譲り受け、本園の温室に植えました。1991年11月に開花し、日本で初めての開花記録となりました。その時の花茎の大きさは直径98 cm、高さが128 cmほどでした。また、1993年に入手した種から育てたショクダイオオコンニャクが、2010年7月・2015年9月にも開花しています。
ショクダイオオコンニャクは、花茎の中心部から伸びる付属体と呼ばれる棒状の器官が発熱して不快な臭いが拡散します。付属体の根元におしべとめしべが2層になって取り巻いています。付属体のおしべ層の上部は膨らんでいておしべとめしべの蓋をするような形になっています。この臭いに惹かれて集まった虫(シデムシ)は、花に引き込まれ花の中に閉じ込められ花粉をまとわされることになります。蓋になっている付属体は、2日間ほどで臭いがなくなり機能しなくなり虫は花から解放されます。放たれた虫は次の花の臭いに導かれ、森の中の次のショクダイオオコンニャクを目指すことになります。これが自家不稔性(自身の花粉により受精しない性質)であるショクダイオオコンニャクの繁殖戦略です。このような不快臭は、夜の虫といわれる甲虫類やハエ等の誘引に有効だと考えられます。
この記事を執筆中の2023年11月の上旬頃、ショクダイオオコンニャクの花の蕾が成長を始め、12月7日~8日の夜間に開花しました。高さ215 cm、仏炎苞の幅が110 cmに成長し、本園では今までで一番大きな花となりました。腐肉のような臭いに負けず付属体の根元を撮影しました。特別公開は12月8日~12月10日の期間行われ、多数の見学者が来園されました。


香りで自己防衛する植物
植物の持つ香りには、葉や茎の食害を受けないための自己防衛のためのものもあります。皆さんもよくご存じのシソ科のハッカやミカン科の柑橘類、クスノキ科のゲッケイジュやクスノキなどは、葉や幹・実に精油成分が含まれており、それを人間は良い香りと感じているのですが、植物が動物や害虫に食害されないために獲得した工夫です。
花の色や蜜・香りで誘う植物
蜜や花の外観で受粉を促す植物の例として、本園の温室にはサガリバナやヒスイカズラの仲間があります。
○ヒスイカズラ
フィリピン原産のマメ科のヒスイカズラ(絶滅危惧種)の花には良い香りはありませんが、花は非常に鮮やかな翡翠色(ひすいいろ)で蜜がたっぷりと出ます。コウモリや小動物などが、甘い蜜を求めて花に顔を突っ込むことで受粉し花粉の運搬を手伝ってもらっています。受粉した実はとても大きく熟して、落下するとはじけて中の種(豆)が飛び散る仕組みになっています。種が地面に達すると、すでに発芽しておりすぐに生育を始めます。
花は自家不稔性といわれており、めしべには容易に花粉が付かない構造になっています。自然界ではコウモリが受粉を手伝っていると考えられていましたが、本園の実験では筆でめしべの柱頭の先をこすり、傷つけて花粉が花粉管に入りやすいようにして人工授粉を成功させました。この研究の成果でヒスイカズラの人工繁殖ができるようになりました。


○サガリバナ
サガリバナ科のサガリバナは、水辺のマングローブ林に生育して一夜に開花する短命の花です。花の甘い香りで夜に訪れる昆虫やガやコウモリを誘い、受粉を促し翌朝には花は散ってしまいます。植物の受粉(生殖)は他の個体から新しい遺伝子を獲得することで進化を促し、種の多様性を保とうとする野生生物の巧みな戦略だと考えられます。


植物園と種の保全活動
欧州の先進国や英国は、ロンドンの王立キュー植物園に代表されるように大航海時代(15世紀から17世紀頃)から冒険航海を通して、新大陸や未開地を調査して世界中から有用な植物資源を探していました。探検者や植物の研究者・プラントハンターと呼ばれる植物の知識を持った人たちを世界各地に派遣し、自国の繁栄のために有用な植物を見つけ研究し植民地に移植することで栽培・繁殖(プランテーション)し、他国に輸出することで外貨を稼ぎ自国に富をもたらしてきました。皆さんもよく知っているゴム、紅茶、香辛料、コーヒー、ココアなどがこれにあたります。同様な植物資源調査は、日本を含めた先進国で行われており、100年以上前から多くの学者が資源調査の目的で世界各地に派遣されています。
小石川植物園の保全活動
戦後の日本でも、植物調査で世界各地に植物学者たちが入り、様々な植物を日本に持ち帰り研究してきました。その未知の植物を預かって繁殖させるのが、私たち植物園の技術職員の重要な仕事のひとつとなっています。1960年以降は、国内の調査にとどまらず、東アジアの広い範囲の野生植物の調査・研究・保全が小石川植物園のテーマになっており、アジア各地で調査収集してきた植物や海外の植物園との種子交流事業で手に入れた珍しい植物を本園のバックヤードで研究し育ててきました。
戦後に海外の植物園との種子交換で入手して育てた貴重な苗を圃場で育ててきましたが、大きく育ち園内に移植するのも困難な状況となりました。それらを打開するために、1970年頃から職員による園内の不要樹木の伐採を伴う植生配置計画が立てられて行われてきました。
1980年代には京都大学から岩槻邦男教授が小石川植物園に赴任され、園長になられると「種の保存」「生物多様性保全」「野生生物の持続可能な環境の研究」を国や社会に呼びかけました。また、㈳日本植物園協会の会長となった岩槻園長は、全国の植物園での「野生植物の保全」活動を広めて、1986年に東京都が「絶滅に瀕する小笠原固有植物の育成・増殖研究」として事業化し、1994年に環境省事業となり、小笠原希少野生植物保護増殖事業として現在に至っています。
今日、世界的に生物多様性の保全(種の保全)という概念は当たり前のように使われるようになりましたが、1990年頃に植物園の持つ使命が「生物多様性を保全する活動」であると位置づけられたことで、本園の整備計画に「野生植物の保全のための研究」という明確な方向を持つことになりました。私も野生生物(植物)の保全や繁殖を研究するために、1990年頃から白神山地や尾瀬、日光、白馬山、八甲田山、鳥海山、早池峰山、月山・湯殿山、大台ケ原など様々な場所をめぐって、野生植物の生育する環境を調査してきました。この調査で得られた経験を糧に、植物園で育てる様々な植物の栽培に生かしてきました。


牧野富太郎が発見したアテツマンサク
2008年には、小石川植物園で栽培されていたマンサク科のアテツマンサクHamamelis japonica Siebold et Zucc. var. bitchuensis (Makino) Ohwiが、近傍の倒木の巻き添えとなり枯れてしまいました。現場でどう対応するか考えているところに、牧野富太郎がアテツマンサクを新種として発見した岡山県新見市(旧阿哲郡)の新見市商工会議所の方が来園されました。事情を説明したところ、阿哲郡という地名が新見市に編入されて消滅する時期でもあり、市長にマンサクを寄贈してもらえるように嘆願してみようということになりました。
新見市からマンサクの苗を寄贈してもらえる話が決まり、2008年10月に新見市市長に御挨拶に伺い、現地のタイプ標本(最初に命名して発見した時の証拠品となる標本。DNA解析もできる)を採集した黒髪山の原木を確認して、そこから株分けされた苗木を分譲していただきました。2008年11月11日に新見市長石垣正夫等に本園にお越しいただき、植樹式を行い新たに導入することができました。


植物の様々な繁殖戦略
植物は種の保存だけでなく、繁殖にも様々な戦略を駆使しています。その方法をいくつか紹介しましょう。
菌類と共生する植物
菌根とは、菌類と植物の共生の一種で菌類が植物の根の組織の内・外に付着または侵入して養分の授受などの協力した関係が成立している状況を菌根と呼び、菌根を形成する共生菌のことを菌根菌と呼んでいます。陸上植物の8割が菌根菌共生しているといわれており、菌糸が根の組織内に侵入する内生菌根(アーバスキュラー菌根・ラン型菌根・ツツジ型菌根など)と菌糸が根の組織の表面に付着し菌糸層を形成し働く外生菌根(担子菌類・子嚢菌類、キノコの仲間)とその中間型があります。
アーバスキュラー菌根菌は、草本植物を中心に広い分野の植物と共生しており、土壌からリンを吸収して植物に提供し植物の生育を促進し、他の菌類の侵入を防ぐことにより土壌病害や生理障害を軽減するなどの効果が認められ、菌根菌の研究が進めば農業への応用にも期待されます。
菌類を利用する植物 ラン
ランの仲間の種はとても細かい粉状であるため、自身で発芽して成長するだけの栄養を持っていません。種が地面や土に降りるとそこに生育する菌類や植物の根と共生することで栄養をもらってはじめて発芽し生育できるようになります。
根粒菌と共存する植物 レンゲソウ、シロツメクサ、ハンノキ
田んぼや畑の緑肥として利用されてきたマメ科の植物〔レンゲソウ、シロツメクサ(クローバー)など〕では根の中に根粒菌を住まわせて(根粒共生)、空中窒素固定能力を用いて根粒菌から栄養(窒素分)をもらう戦略を持っています。
カバノキ科のハンノキは、肥料木と呼ばれ高山や水辺の栄養状態の悪い土地でも生育できるように、根の周りにいる根粒菌を住まわせ栄養を受け取り生育します。瘦せた土地に先駆植物としていち早く生育できますが、土壌が肥沃になると他の樹木が侵入してきて徐々に他の樹木に置き換わり遷移していきます。
ハンノキが根粒菌と共生しながらあまりに大きくなると土壌の栄養が不足してしまうので、成長を抑制させる機構や植物が菌類の繁殖のお手伝いをする仕組みなどがあることが、近年の根粒菌共生の研究で分かってきました。
菌根菌共生で栽培が改善
園芸業界では、昔からランやツツジの栽培家などの間で菌根菌共生があるのではないかといわれていました。それが近年検証されつつあるという段階なのかもしれません。
植物と菌類共生の可能性
植物の生育環境をつぶさに調べ分析することで絶滅に瀕している植物の栽培環境の改善をはかるヒントになるかもしれません。現地の植物が好む栽培環境が見つかれば絶滅危惧種が自ら繁殖し生育できる環境も整うと考えらえます。
動物の力を借りる植物
温室にアジアの薄暗い環境で育つイワタバコ科のモノフィレアMonophyllaea という、生涯1枚の葉で過ごす不思議な植物があります。温室係はそれを研究する教授のために、日本に種子を持ち帰り栽培を試みましたが最初はうまくいきませんでした。しかし、調査中に洞窟にコウモリがたくさんいたことを思い出して、コウモリの糞でできた肥料を取り寄せ施肥したところ栽培がうまくいったという例もあります。
栽培技術者の中には、生育条件を厳格に守る人と遊び心をもってチャレンジする人がいます。私は未知な植物の栽培においては、多様で柔軟なアプローチがあってよいと考えています。時にはとっぴな発想も必要ではないかと思っています。


植物を取り巻く環境問題


地球温暖化の影響で増加する害虫
近年地球温暖化の影響で気候変動が大きく、また、気温の上昇で今まで見たことのないような新しい病害虫も増えてきています。園内の植物の栽培環境を保つのも極めて難しくなってきています。本園でも20年程前から今まで見たことのなかった害虫が南方から北上してきて、温暖化の影響で越冬できるようになり植物の被害が増加してきています。
植物に被害をもたらしている代表的な外来生物は、ソテツの害虫のクロマダラソテツシジミ、サクラの害虫のクビアカツヤカミキリやツマアカスズメバチなどです。
人間の活動による山林の荒廃
地球温暖化の他にも、人間の経済活動によって植物の生育環境が大きく変化してしまった例もあります。戦後の日本の復興期には、農林水産省の指導で真っすぐで製材しやすいスギ・ヒノキが大量に日本の山地に植林されました。その緊急対策が、現在スギ・ヒノキによる花粉症の元凶になっています。手入れの良いスギ・ヒノキ林に入ると間伐が行き届いていて明るく下刈りもしてあるので、林床(林の下)に生える植物は十数種類見られますが、手入れされていない暗い林では1~2種類見つかればよい方で、ほとんど植物が生えないくらいひどい状況も見られます。このような環境の山では、山の保水力は極めて低く土砂崩れの原因にもなります。
戦後の1950年頃の里山では燃料として枯れ枝を集め、薪として利用する薪炭供給林として利用していました。さらに落ち葉を集め腐葉土を作り利用することで、林床の明るさが保たれていました。手入れの行き届いた里山の林床では、現在は珍しくなってしまったキンラン、シュンラン、カタクリ、ヒロハアマナ等の明るい林床の生育に適応した多様な植物群が見られていたのですが、家庭にガスや電気が普及して薪や炭を使わない生活の中では、回収されない落ち葉や枝が山林に残り手入れをしない林や放置竹林が広がり山林が荒れた状態になっています。
里山の手入れの悪い林床ではこれらの野生植物は生きていけません。近年それらを見直し手入れを行うことで希少な植物を守ろうとする活動が始まっています。


野生動物による食害
野生動物は、植林された食物の少ない山から川を伝い、手入れが悪い林を伝わって食べ物が豊富な里山や都心部に現れて農作物や人に大きな被害を与えています。これは山林や里山の整備を怠って動物との生活圏の境界線をあやふやにしてしまったことと、温暖化で冬の冷え込みが弱くなり積雪が減った冬季には、本来の寒さで自然淘汰されていた野生動物が生き延びてしまい数が増えてしまった結果です。増えすぎた野生動物は広域に移動し高山に登り高山植物を食べ荒らし、様々な貴重な植物や植林したスギ・ヒノキの表皮などを食害し森を枯らすというような事態が日本各地で発生しています。地球規模での気候変動や温暖化は人間の活動による弊害であることはあきらかで環境問題に配慮せずに便利な生活を享受してきたことに原因があると考えられます。COP(締約国会議:198か国の国の機関が参加する気候変動に関する国際会議)などの提言に従い脱炭素の取り組みや地球規模での気温を下げるような工夫や技術(砂漠の緑化、農業技術の改良、地熱発電など)を必要とするのであれば、国家戦略として今からすぐに取り組まなければならない問題だと思います。
現在、私の住んでいる埼玉県の武蔵野地域では、昔ながらの落ち葉の堆肥利用や土壌飛散防止など複数の機能を持たせた「武蔵野の落ち葉堆肥農法」が日本農業遺産に認定されました。昔は普通に行われていた雑木林の手入れを、農業や生活に取り入れ利用することで多様な里山の植生が保全されます。人間がかかわり利用することで、自然環境が良くなり里山の多様な生物は生きてゆけます。戦後すぐのレトロな生活スタイルも研究してみると環境にやさしい豊かな生活をすることができるかもしれません。
江戸時代のエコ生活に習う
江戸時代には、木地師と呼ばれる木を使用して食器・雑器などを作成する職人がいて、全国の野山を回り、様々な樹木を使って商品を作るのと同時に木を植えて育てながら保全して生活していました。江戸の町人は、長屋の共同便所のし尿を近隣農家に売ってその代金で野菜を買うなど、今でいう循環型エコシステム社会を構築していました。それらに学び無駄なエネルギー消費を減らして、効率の良く環境にやさしい生活に近づけていく工夫を続けてゆくことができれば自然環境は保たれると考えています。
戦後、国の政策で植えた山林のスギやヒノキは少なくとも建材や建具で利用するために伐採し、建材として有効に利用してほしいと考えています。木製品は温かみがあるし手入れをすれば長持ちもします。木は適切に加工をすれば長く利用できます。手入れの悪いのこぎりで木を切断すると、木の断面がささくれて樹木の細胞の表面から水が浸み込み腐食しやすくなりますが、鋭利な刃物で適切に加工すると木の細胞はきれいに切断され呼吸ができるため木材は長持ちします。奈良の法隆寺のような木造建築物が長持ちしているのは、木材の性質を理解した宮大工が、釿(ちょうな)などの鋭利な刃物を使い削りだして腐食した木材の部分を切り出し適切に交換しているからだといわれています。
木の性質が分かって使用していると、同じ材料を使用しても耐久性が格段に違います。マツ材は油脂が多く水に浸かっていると腐食しにくいため川岸の杭に利用されます。同じ加工を施してヒノキ丸太を杭に利用すると数年で朽ちてしまい耐久性には大きな差が発生します。植物園の池の護岸工事でもマツ杭とヒノキ丸太を利用しましたがマツ杭は20年以上持ちこたえ、ヒノキ丸太は5年で朽ち果てました。取るに足らない事柄ですが、工事内容を細かく分析することで無駄を減らし、自然に対する環境負荷を大幅に減らし、工事の耐久年数を伸ばすこともできると考えています。
生物の力を利用する温暖化対策
地球規模での気候変動対策として、地球の持つ力を利用することや、植物や菌類・微生物等の持つ化学反応や分解反応の可能性は大きいと思います。地上にある植物だけでなく、海洋にある海草類をはじめとする海中の動植物・微生物等も研究(藻や海藻などを介して炭素を海洋生態系へ取り込み削減をはかる取り組み・ブルーカーボン)すれば利用できる可能性が広がります。そのためには、水質の浄化や海底まで光の届く浅瀬の保全が不可欠となります。
都市の生活環境を守るために河川の護岸をしっかりとコンクリートで固めてしまったのでは、山林や陸地から供給されるミネラルや砂礫が減少して砂浜や浅瀬も痩せてしまい、そこに住む生物層に影響を及ぼします。川の氾濫は抑えられても、山からの土砂やミネラルなどの栄養分が届かないことで、砂浜や海藻等も減少して磯焼けが発生してそこに生活する魚類やサンゴなどの生物も危機に瀕することになります。自然環境サイクルと科学的根拠のある情報の共有や理解は自然保護と持続可能な社会の実現の第一歩となります。
絶滅危惧種を守るために
小石川植物園の温室には、50年も前から絶滅危惧種のキツネノマゴ科のミヤコジマソウが繁殖しています。温室内では繁殖力が強く容易に枯れませんが、生育地の宮古島の海岸では護岸工事が進んだために絶滅危惧種に指定されています。希少な植物があることを知らずに護岸改修工事を行った人たちの理解の問題です。最近、「環境アセスメント」という言葉が死語になったような気がします。
工事を進める前に、事前に森や文化に対する研究や調査を行う。工事を進めた場合どのような被害が発生するか。その対応はどのようなことができるか。工事前に調査すると考えていましたが、神宮外苑の再開発のための樹木の伐採問題では、施工設計以前に住民と自然文化や環境計画等の協議をしなければならないはずなのに、それは後回しにして工事計画案が完成してから発表されるのでは、「そこは変えられません」という話になってしまうのは当たり前です。本来、環境アセスメントは計画前の段階で住民や文化人を交え平等な立場で協議を行い、計画を共に作り上げるために行うべきだと考えています。住民や自然・文化・環境の評価を軽んじていると自然環境に大きな影響が発生すると思います。


人類を支える自然資源の計画利用と再生
昔から、大きな文明が栄えた後は砂漠しか残らないといわれており、エジプトやメソポタミア文明の跡は周囲に砂漠が広がっていますが、かつての中東一帯には豊かな森林が広がっていたといわれています。現在は石柱のみが残っているギリシャ神殿の遺跡も、かつては屋根に大きなアトラスシーダやレバノンスギ(マツ科)等が使われていたといわれています。
つまり周辺に、文明が発展するのを支えるだけの森林資源があったはずです。しかし、文明が発展した後は砂漠になった。荒地しか残らないでは、次の時代を生きる人たち(子孫)が疲弊してしまいます。人類は発展のために利用した森や海を再生して、次に渡す工夫をしなければならないはずです。これは化石燃料を大量消費して現代文明を繁栄させ謳歌してきた今を生きる大人の責任でもあり、人類すべてが共通の問題として認識し、叡智を結集して解決していかなければならない問題だと思います。
次の世代に受け継ぐこと
現在、日本人の年齢構成が大きく変わって高齢化が進んでいます。どうやって若い世代に負担をかけずに効率よく引き継いでいくかが、今重要な問題になっています。
植物園の維持と植物生育への工夫
私が植物園に勤め始めた時には技術職員が12名いましたが、現在(2023年)は6名に半減しています。少ない人数で同じだけの面積と高度な仕事をこなすために、合理化と機械化を進めてきました。それでも植物を育てるための植え替え、灌水、施肥・薬剤散布などのアナログな作業が残りました。この一見あまり価値のないような毎日の仕事に実は植物をうまく育てるコツが潜んでいます。
毎日植物を気にかけ観察することで、今何を必要としているかを探り出しています。すこしだけ面倒だけれど、確実に進めてきた仕事には必ず大きな実りがあります。効率よく作業を行うような小さな工夫がいろいろ集まれば、環境問題を解決する小さな答えになるように思います。小さな結果が集まれば大きな成果も生まれます。
日常生活の見直しと自然循環の研究
例えば一般的な農作物を作るのであれば、土壌を耕し施肥を行い作物を植え育てますが、作物との親和性の高い菌根菌を見つけ肥料のように使えれば、大量の化成肥料を使用しなくても効率よく農業を続けることができる可能性があります。
一つの畑で単一の作物を栽培する方法だけでなく、複数の作物を同時に栽培する(複合的農業)ことで害虫被害を軽減できる農法も研究されています。化成肥料の大量使用の反省から荒れてしまった農地を回復させるために、輪番制で様々な作物を順次作付けし緑肥を施す栽培方式に切り替えれば土壌の持つ力を落とさず栽培することもできます。
栽培技術を見直すために、その地域固有の古い栽培技術や知識を掘り起こすことで、新たな解決策を見つけ出すこともできると思います。地球環境のつながりの中で、当たり前に享受していた生活スタイルを見直し研究することは自然環境の破壊をくい止め、自然循環(自然の循環の中でのつながり)を取り戻すことでもあるでしょう。
植物の栽培では、もっと効率的で環境にやさしいやり方があるのではないかといつも考えます。毎日の生活排水やし尿処理一つとっても、微生物をうまく使えばガスやアンモニアに分解し回収して資源にできる可能性があり、現代的な循環型エコシステムも構築できるのではないか、残飯も廃棄物も発酵させればガスを回収できるし残りを肥料にすることもできるはずです。街路樹を伐採すると焼却場で燃やしますが、熱で発電しながら給湯に利用し灰も肥料にできると思います。現在、国土交通省によって下水道革新的技術実証事業(B-DASHプロジェクト)で、下水道の資源化に関する様々な実証事業が行われています(バイオガス、リン、水素回収、発電、汚泥固形燃料化、給湯、水の再利用など)。近い将来これらの技術が世界の環境を改善することに貢献するかもしれません。
以前は小石川植物園でも倒木は伐採して、たき火で燃やしていましたが、近隣への影響を考え廃棄するようになりました。自前で燃やしていた頃は、灰をふるって肥料として使ったり、釉薬として使うという焼き物工房に引き取られたりしていました。灰肥料は、土壌改良に有効なだけでなく土に混ぜるとモグラを寄せ付けない効果もあります。木の焼けたにおいを野生動物が本能的に嫌うためだといわれています。
自然環境の保全と生物の多様性保全を目指して
生物や植物には環境適応能力があり多様な進化を遂げてきました。地球上の自然環境に存在する様々な生物を研究することには大きな可能性があり、地球規模での環境問題が顕在化している今こそ研究することに意義があります。世界各地の研究者や技術者が多様な情報を持ち寄り地球上に住む植物や生物の生態を知ることは多くの気づきを与えてくれます。私たちは植物園での学びから様々な情報を読み解き新しい技術と農林水産業や全産業の情報を融合させ研究することで自然環境を取り戻すお手伝いができると思います。私たちは、植物園での生物多様性保全の研究を通して市民の健全な憩いの場であることを起点として、そこで優れた生涯学習機関として活用される体制を整え、そのバックヤードとしての研究機能を充実させ社会の自然環境を守る情報の発信を続けていきます。


付録:小石川植物園について
小石川植物園は、1877(明治10)年に東京大学の附属植物園として開園してから147年(2024年現在)になります。ここでは小石川植物園の歴史と園内の見どころをご紹介してみたいと思います。
小石川植物園の歴史
小石川植物園の前身は、1655(承応4)年に舘林藩の松平徳松(第3代将軍徳川家光の子、後の第5代将軍綱吉)に、小石川の下屋敷の土地として与えられ舘林藩小石川下屋敷が建てられ、綱吉の将軍就任に伴い幕府の所持する小石川御殿(白山御殿)となります。
1684(貞享元)年に、敷地内に江戸幕府が麻布の南薬園を移し小石川薬園の先がけとなります。1709(宝永6)年に綱吉が没した後の1713(正徳3)年に小石川御殿は廃止され建物は撤去されますが、その後も幕府の御薬園は芥川小野寺と岡田利左衛門(世襲制)の薬園奉行に預けられ江戸幕府が倒れるまで続くことになります。
1722(享保7)年には、御薬園内に施薬院屋敷(小石川養生所)が設けられます。1735(享保20)年には、江戸幕府第8代将軍徳川吉宗に、飢饉を救う作物の試作を青木昆陽が願い出て甘藷の試作栽培を行いました。江戸幕府が倒れ明治時代に移ると、小石川薬園は東京府管轄大病院附属御薬園に引き継がれ、1875(明治8)年に文部省所轄教育博物館の所属になり「小石川植物園」となります。1877(明治10)年には東京大学の所属となり、現在の植物園の歴史につながります。
1897(明治30)年には、本郷(東京帝国大学)から植物園に植物学教室が移転してきて、初代の園長松村任三教授がこの時期に園内をイギリスのキュー王立植物園に倣い整備しました。現在の植物園地図の園路の配置は、この時に決められた位置がおおむね引き継がれています。
1923(大正12)年9月1日の関東大震災や先の戦争による空襲〔1945(昭和20)年5月25日〕で、園内は荒廃しました。戦後の様々な困難な時期を乗り越えて、国内外の植物園や植物調査で得られた植物を園内に植栽しながら植物園はゆっくりと復旧してきました。
2012(平成24)年9月19日に「小石川植物園(御薬園跡及び養生所跡)」として、名勝及び史跡に指定されました。
小石川植物園の特長
面積は約16万1588m2(4万8880坪)で、高低差のある変化に富んだ地形を利用して多様な植物が配置されています。園内の栽培植物総数は、約1500種あり約7000本の樹木が植栽されておりそれぞれにストーリーがあります。100年以上この地に立ち続けている木、日本各地から運ばれてきた木、戦火に耐えた木など様々です。その中のほんの一部をご紹介します。


【施設、標本展示】
- 植物園本館(①)には、事務室と研究室があり植物園の環境で研究を行っています。植物標本80万点と植物学図書2万冊が所蔵されており、植物研究に利用されています。(非公開)
- 2019年に新設された公開温室(②)は、ランや小笠原諸島の絶滅危惧種、有用樹木や希少な植物をはじめ熱帯・亜熱帯産の植物約2000種、冷温室では日本の北部や山地に見られる植物を中心に展示。
- 薬用保存園(③)では、江戸幕府の御薬園前身であったので薬草類120種を展示、大学の研究・実習施設として植物分類標本園(④)では約600種、シダ園(⑤)では約120種を展示。
- 山地植物栽培場(ロックガーデン)(⑥)では、山地や里山の植物を保全しています。(非公開)
【並木、樹木林】
- 温室前のイロハモミジ並木(⑦)やサクラ林(⑧)は、四季を通じて目を楽しませてくれます。
- 自然を味わえる常緑針葉樹林のスギ・ヒノキ林やカリン林(⑨)、第三紀植物群林の生きた化石メタセコイア林(⑩)、ラクウショウ林の不思議な呼吸根(⑪)、戦禍を生き延びたヒマラヤスギ林(⑫)、明治初期に西洋街路樹として初めて導入されたスズカケノキやユリノキの巨木の杜(⑬)、常緑広葉樹林にある園内最古の薬木サネブトナツメやカシノキ類などの森林(⑭)。
- 南斜面を利用した南方系樹木林、高低差を利用した育成を行っている常緑性自然林と二次林。
- 園内の小径ではコゴメイヌノフグリ、オオアマナ、ハナニラ、ムスカリ、フジ、ツツジ類、ナツズイセン、キツネノカミソリ、ヒガンバナ、ツバキ、サザンカなど季節ごとに様々な植物に出会えます。
【庭園・池】
- 日本庭園(⑮)は、徳川第5代将軍綱吉の下屋敷跡と伝えられる庭です。「都会の中にあるのに、南側から望むとビルが見えないところが素晴らしい」と来園者に人気の高い場所です。
- 東西に広がる池は湧き水を利用しており、ハナショウブ(⑯)が約50種200株植えられています。水生植物栽培地では、ザゼンソウやミズバショウなども見られます。
そのほか、本記事でご紹介した精子発見のイチョウ(⑰)やソテツ(⑱)をはじめ、様々な古木や巨木や多様な植物たちに出会え、季節ごとの風景を楽しむことができます。また、養生所井戸跡、御薬園乾薬場跡、青木昆陽「甘藷試作跡の碑」、関東大震災記念碑などの歴史的な遺構を散策の途中に見つけることができます。
詳細は小石川植物園のホームページ(https://koishikawa-bg.jp)でご紹介していますのでご覧ください。
- 山口 正 やまぐち ただし
-
東京大学大学院理学系研究科附属植物園育成部技術職員
1978年東京大学理学部附属植物園に技官として採用。1980年小石川植物園社会教育企画委員。1986年樹木園係に移籍後、園内樹木の植栽図を作成。1997年植物園植物分布記載システムを整備。2005年㈳日本植物園協会第39回大会「東京大学植物園における植物登録システムの変換」を報告、日本植物園協会誌第39号(2005年3月)に投稿。1999年~日本庭園護岸改修工事の意匠を監修、古い植物園施設図・工事関連の歴史資料の編纂を始める。2012年9月名勝及び史跡 小石川植物園(御薬園跡及び養生所跡)指定のための資料提供。2015年東京大学総合博物館ニュース Ouroboros Volume 20/Number 1「祝!ハナミズキ来日100周年」池田 博・山口 正。2014年~2022年温室改築時の埋蔵文化財調査に情報提供。(2019年)温室施設展示物、小石川植物園温室案内、(2019~2020年)ミニ企画展「小石川の温室いま・むかし」の展示に資料提供、(2023年)ショクダイオオコンニャク栽培記録等の情報を温室の展示・頒布物に資料提供、小石川植物園後援会発行 小石川植物園案内(1984年)、ハンカチノキ(2000年)、小石川植物園と日光分園(2004年)の編集に参加、巨大コンニャクのなぞ タイタンとギガス(2010年)に写真や栽培情報を提供、趣味の園芸 気分爽快 植物園さんぽ Vol.1 小石川植物園 取材 NHK出版(2020年4月)
見出しのみを表示する