香りと多様性
~広がり続ける香りの世界~



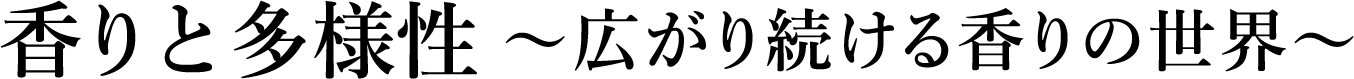

多様性は現代の重要なキーワードです。価値観の多様化により、ライフスタイルにも変化がみられます。香料においても日常生活では個性の演出や、リラックスのために活用されています。さらに食生活でも嗜好や飲食シーンが多様化するなか、香りがどのような役割を果たしていけるか興味の湧くところです。2025年のHASEGAWA LETTER onlineでは香り周辺の多様性についてさまざまな角度からのアプローチを試みます。

THトピックス
![]()
自然科学香話
![]()

社会の中の香り
![]()

OUR 技術レポート
![]()

OUR 技術レポート
![]()

OUR 技術レポート
![]()

カオリ to ミライ
![]()

THトピックス
![]()
THトピックス
![]()
THトピックス
![]()
THトピックス
![]()