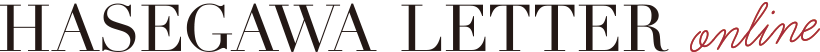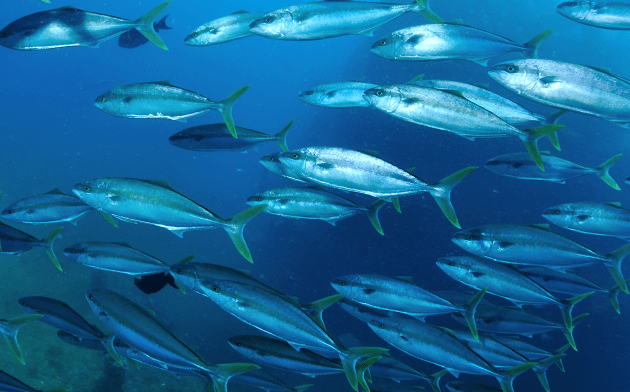HASEGAWA LETTER 2023年( No.41 )/ 2023.01


社会の中の香り
おいしい料理 ~料理人が追い続ける幸せの香り~
コーポレートシェフという職種があることをご存じでしょうか。私はホテルシェフとして30年以上勤めたのち、長谷川香料のコーポレートシェフを務めてもうすぐ10年になる料理人です。ある日HASEGAWA LETTER編集部から「おいしい料理を食べると幸せを感じますよね。料理人にとって『おいしい料理』って何ですか?」と聞かれました。とんでもなく難しい問題だ!というのが正直な感想。そこで、一料理人として思うことをつづることとしました。
料理との出会い、そして料理人へ
私は料理上手だった母の影響を受け、小さい頃から食べることも料理をすることも好きでした。小学生になるとインスタントラーメンやカレーを作っては家族に食べてもらったり、理科の実験のような料理を試したりもしました。今思うとちゃんとしたものができていたのでしょうか。そういえば、私が作った料理を家族は喜んでくれましたが、おいしかったかどうかわかりません。
ホテルでの修業時代
中学・高校では部活に励み、高校卒業後、調理師専門学校に通っていましたが、就職の時期になっても友人のバンドの手伝いに打ち込むのんきな就活生でした。卒業間近になって慌てて担任の先生に相談すると、ちょうどホテルニューオータニの調理部門に欠員が出たとのこと。運よく推薦してもらい試験を受けどうにか合格。私の料理人人生の幕が上がります。
私の入社当時、ホテルの調理部門に入る新人は、鍋や食器洗い、フロント、キャッシャー、サービスなどの仕事を数年間経験しないと調理場に入れなかったのですが、運よく欠員が出たのが調理場でしたので、私はすぐに調理の現場に入ることができました。調理場に入ったとはいえ、新人のやることといえば、マシンでの大量のタマネギのみじん切りや、生クリームの泡立て、先輩が使う食材を冷蔵庫から持ってくる、きれいに盛り付けられた料理を宴会場まで運ぶというようなもの。レタスをちぎるくらいはさせてもらっても、包丁を使って食材を切ると「こんなのじゃ使えない!」などと怒られっぱなしの落ち込む日々が続き、当時はそれが当たり前という非常に厳しい職人の世界でしたので、毎日辞めることばかり考えていました。
ホテルの調理部門は一般企業と同様に人事異動があり、1カ所のセクションにずっといるわけではありません。私も2年目になるとホテル内のコーヒーショップに移り、パントリーというデザート系やソフトドリンクなどを担当する部署で仕事をすることになりました。そこでフルーツパフェやプリンアラモードなど、フルーツを切ってのせて、ホイップクリームで盛り付けるという、自分で作ったものをそのままお客さまに出すことができる立場になりました。ですが、そこは1000名の朝食を賄う日本一忙しいコーヒーショップとして名を馳せていた店。ラストオーダーを深夜1時に終え、仕事の遅い私は仮眠の時間もなく朝の3時から調理場に入り、お昼の12時まで猛烈に忙しい毎日でした。仕事が終わるとへとへとになり、家に帰り着いたらすぐ寝てしまうという生活が続いていて、本来なら他店を食べ歩き、フルーツの切り方や盛り付けを勉強したかったのですが、それもなかなかかなわない状況でした。
今では考えられないような昔の話です。
フレンチとの出会い
忙しさと先輩の厳しい指導に悩んでいた頃、パリに本店のある当時ミシュラン三つ星の鴨料理で有名なレストランがホテルニューオータニに進出するという情報を仲の良い先輩に教えてもらいました。当時、星付きの本場フランスのレストランが日本に支店を出すということは初めてで、私も大いに期待が膨らみました。そこで仕事が終わった後、先輩と一緒に語学学校でフランス語を勉強し、異動の希望を出し、そのレストランのオープニングスタッフとして参加する機会を得ました。料理人としては駆け出しの時期、本場のフランスのシェフに出会い、知らなかった食材に触れ、フレンチの基礎を叩き込まれたことは私にとって大変貴重な体験でした。知らない味、料理を覚えること、何よりそのような場所で働けることの満足感。日々喜びがあり、もっと知りたい、もっと勉強していきたいという充実感で満たされていました。もちろん仕事が厳しいのは当たり前。しかし良き指導者、先輩に恵まれたことは私の宝物であり、フレンチの料理人としてのベースができあがった時代だったといえます。
世界の料理と文化に触れる そしてコーポレートシェフへ
その後はホテル内のイタリアン、パーティー会場の料理担当、地方のグループホテルのシェフなどさまざまな調理場を担当し、料理人として技術を磨き、時には本場ヨーロッパの国のシェフのフェアに参加し交流をもち、文化を学んだりその国のおいしさに気付かされたり、新しい知識の吸収には事欠かない年月を過ごしました。この間には何千人というお客さまに料理を提供してきました。
そんな中、ホテル時代の上司であった長谷川香料のコーポレートシェフから、調理実習の講師を手伝ってくれないかと依頼され、年に2~3回お手伝いをすることになりました。数年たった頃、シェフが定年退職をされるので、その後任としてスタッフに加わってもらいたいと、大変光栄なお話をいただきました。その時は50歳を越えていましたし、転職の「て」の字も考えていなかったので、とても悩みました。でも、必要とされるのであればチャレンジしてみようと決断し、長谷川香料に飛び込みました。その話はあとで詳しく述べることとしましょう。


フランス料理の基本と進化するフレンチ
フレンチのソース
“フランス料理はソースが命”と昔からいわれていました。どこまで基本と言っていいのか、多岐にわたるとしか言いようがありません。まず、ソースを作る前段階のベースとして、フォンドゥヴォー、チキンブイヨン、ソースドゥミグラス、フュメドゥポワソンなどがあります。それにワイン、エシャロットやマッシュルームなどの香味野菜を加えて煮詰めたり、それらを生クリームで仕上げることもあります。
オマールエビなどから作る「ソースアメリケーヌ」、ステーキにはマデラ酒を煮詰めてフォンドゥヴォーやソースドゥミグラスを加えた「ソースマデール」や赤ワインを使った「ソースボルドレーズ」など。フォワグラにはポルト酒を使ったり、ジビエ料理の中にはレバーをすりつぶしたものや血を入れてつないだソースもあります。仕上げる料理によって、またその時の場面によってさまざまなタイプのものを使います。クラシックなフレンチでも数えきれないソースがあるのです。


日本の新しいフレンチ、味覚に優れた日本人
現在はクラシックのフレンチの伝統が守られる一方、年を追うごとに料理のイノベーションを繰り返しながら、新しいフレンチが広まっています。10年たてば、食材や味付け・調理法も盛り付けも大きく進化するのです。今はシェフがおいしいと思えばバターや生クリームだけではなく味噌も醬油も使います。その調理法をシェフが確立すればそのシェフのイノベーティブフュージョン料理になるのです。最近では、あえてフレンチとかイタリアンなどとは明言しないお店も増えています。
ヨーロッパのシェフにとって日本の食材は非常に興味深いものらしく、30~40年前にはコンニャクやガリなど和の食材を使い、現地で話題になったこともありました。日本人の料理人もフォワグラやトリュフを使って和食に活かしたり、フレンチに日本の調味料を使うなど、それが今の新しい日本のフレンチにつながっているのも確かです。
日本人はいろいろな味を知っていて、味覚が繊細でそのバランスの取り方がうまく、器用だからおいしく仕上げることができるのではないでしょうか。かつて日本人はとんかつやラーメンを完全に日本の食文化に取り入れた歴史もあり、街にはさまざまな国の料理を提供するお店がたくさんあります。日本人は食に関してはとても貪欲ですし、味覚も優れていることが日本の欧米風の料理への探求だけではなく、バラエティー豊かなインスタント食品の開発につながっているのかもしれません。
料理人が考える「おいしさ」
「おいしさ」の要素
「おいしい料理」とは単純にはいえませんが、食事中もしくは食後に幸福感を感じられる料理なのかと思います。しかし「おいしさ」とは、その料理に対して作り手がどのように考えるか、食する人が何を求めているのか、その人のバックグラウンドや食事の場の環境などが複雑に絡み合い生まれてくる感情であることから、難しさが生じます。
おいしさの要素は、
- ①材料…普通に入手できる食材か、高級食材か、冷凍・インスタント食品なのか
- ②料理を作る人…家族なのか、プロの料理人なのか、こだわりをもって作っているのか
- ③料理…いつもの家庭料理か、お店の料理か、インスタント・冷凍食品か
- ④シチュエーション…日々の食事か、記念日などのイベントか、誰と(一人も含む)、その時の精神状態もある
- ⑤ロケーション…自宅か、お店か、屋外か
- ⑥食経験…地方性、どんな料理を食べてきたか、初めて食べる料理か、食べたい料理かなど
ざっと思いついたものだけでもこれだけありますが、このほかにももっといろいろな条件が考えられます。これらがどんな組み合わせで食事をされるのかで、感じ方は変わるのではないでしょうか。
愛情あるわが家の料理
ミシュランの星付きレストランのイタリア人シェフたちに、今までの中で一番おいしい料理は何かと尋ねたことがあります。すると多くの方が「マンマの料理が一番おいしい!」と答えてくれました。なんの変哲もない素朴なポモドーロのパスタ。おそらくマンマの絶妙な塩加減、煮詰め加減、オリーブオイルの量などもあるのでしょうが、家族で食卓を囲み、作りたてのパスタを食べながら一日の出来事を楽しく会話して過ごしたという思い出も含めておいしい料理と刷り込まれているのでしょう。そんなマンマの愛情がたっぷり詰まった料理には、どんなプロの料理人も太刀打ちできません。
同様に、仕事の接待などで緊張しながら食べ慣れない高級レストランで会食しても何を食べたのかもわからず、帰り着いたわが家で食べる一杯のお茶漬けやラーメンが、とてつもなくおいしい料理と思えることでしょう。
このように、作る側と食べる側、それぞれの条件が組み合わさり、常に同じ答えになることはありません。余韻が長ければいいのか、材料のバランスが取れていればいいのか、あるいは味覚センサーでおいしいと定義した数値が出せればいいのか、料理だけで突き詰めていいのかという基本的な疑問にも突き当たります。結局食べる人に委ねるしかないのかもしれません。作り手として責任を放棄するような言い方ですが、仕方がないのです。作る側としては自分の目指すベストの味まで仕上げ、それを食べておいしいと満足していただけることを常に目指しています。はたして食べる側がそう思ってくれるかどうか、そこがいつも作る側とのせめぎ合いなのかもしれません。


料理人の五感と作り手の責任
料理と五感 ― 香りの重要性
料理人が料理を作るときには、カッコよく言うと常に五感を研ぎ澄ませて作っています。加熱しているときの音の変化(聴覚)、状態の変化(視覚と触覚)、香りの変化(嗅覚)、味の変化(味覚)、それらを見極め、最高のバランスで提供できるよう取り組んでいるのです。実際はそれほどカッコいいことではなくて、料理は一つの動作につきっきりになれるわけではなく、肉を焼きながらほかの材料を切ったりオーブンに入れたり、ソースの用意をしたりと複数の作業を同時にこなさなくてはなりません。そのために常に五感を総動員して気を張っているということだけなのですが。
五感の中でも香りはとても重要です。料理が運ばれてきたときに立ち上る香り、口に含み咀嚼して味覚と一体となった後に鼻から抜ける香りなど、香りがなければ料理のおいしさは半減、いやそれ以上に失われてしまいます。そのため、フレンチではソースを作るときにお酒を煮詰めることもしますが、仕上げにそのお酒を数滴加えて香り立たせるテクニックも使います。


作る責任
人間は感情に支配されがちです。料理人もしかり。料理の味付けなどにも影響が出るので、若い頃は何度も失敗がありました。先輩たちに作ったサラダが「今日のサラダには気持ちが入ってないね。おいしくないよ、いつもと違う」と言われたことがありました。仕事に追われていていい加減な味付けになっていたのかもしれません。自分としてはいつもどおり作ったはずなのに、それを指摘する先輩はすごい、ある意味怖い存在だと改めて感心したことを鮮明に覚えています。確かにイヤイヤ作っていたのですから。どういう精神状態にあるかによって微妙に味覚が変わってしまうことはどうしてもあります。ただし、料理人が今日は家で喧嘩をしてきたからとか、心配事があるからとかはお客さまには一切関係がありません。どんな状況であろうとベストな味に仕上げなくてはいけません。経験値と集中力をもって仕上げる、それがプロなのです。
ホテルのレストランの調理場では直接お客さまの反応を見ることはなかなかできません。中には直接不満をおっしゃるお客さまもいますが、多くの場合、返ってきたお皿をチェックして、たまたまお客さまの好みに合わなかったのか、それともこちらのミスだったのかを判断します。おわびをしたり、作り直すこともあります。海外の方も含め不特定多数のお客さまが利用されるホテルのレストランでは、個人のお店と違いシェフが作ったメニューを何十人ものスタッフが作ります。しかし作る料理人個々人の味の嗜好を反映させてはいけません。あくまでもその「レストランの味」に仕上げなければいけない責任があるのです。毎日何十何百と同じ料理を作り、その中のたった一皿を気を抜いていい加減に作ってしまえば、その料理を召し上がったお客さまは失望し、レストランには来ていただけなくなるでしょう。料理人にとって百皿の中のたった一皿くらいはいいだろうという甘えは許されないし、お客さまにとってはその一皿に期待をしてくださっているのですから。
しかし、お客さまの中には、最初から辛くしてくれとおっしゃる方や、料理が出されてから味も確認せずにすぐタバスコをかける方もいらっしゃいました。作った側からすると、それじゃおいしくなくなってしまうと思いますし、料理を否定されたようで悔しい気持ちにもなりますが、その人にとってはそれがおいしいと思っていらっしゃるので、そこに作り手の料理人の想いとのギャップがあります。
また、私が若く生意気な頃、イタリアの星付きレストランとコラボをするようなホテル内のイタリアンレストランで、「ナポリタンが食べたい」とおっしゃったお客さまがいらっしゃいました。お店のメニューにはなかったのですが、オーダーを受けて躊躇していたところ、シェフから「作ってさしあげなさい」と言われ、「このレストランはバリバリのイタリアンレストランなんだけどなあ…。喫茶店じゃないんだよ!ケチャップだけの味付け?そんなのでいいの?」などと変なプライドで心の中で葛藤しながら作ることにしました。その時に学んだのは、ホテルとは、不特定多数の老若男女のお客さまの望むものは、最大限の努力をしてお客さまに喜んでいただくことであるという責任でした。


コーポレートシェフとして
コーポレートシェフの仕事
ホテルでの料理人としてのキャリアを積みながら、縁あって長谷川香料の一員コーポレートシェフになりました。入社する前は、さぞ香り高い料理を作ることができるのだろうと期待していたのですが、入ってみると……。
香料会社というのはその名のとおり、香料を開発しメーカーに向けて販売するという、表舞台には出ない縁の下の力持ちの立ち位置の会社です。食品に加えられる香料とは、インスタント食品やレトルト食品などの加工食品をおいしくするための「フレーバー」と呼ばれる素材のことです。私の業務の一つは、フレーバリストの作ったフレーバーを実際の食品基材に加えるとどのような効果があるかを試験するための食品基材を調製することでした。
ホワイトソースを例にとると、レストランではバターも牛乳も厳選されたものを用い、シェフの絶妙な火加減や攪拌具合で仕上げ、それを使用しグラタン、ドリア、クリームコロッケなどに調理し高価な値段で提供します。ところがスーパーに並んでいる冷凍食品はそういうわけにはいきません。コストを重視した原料選び、加工の手間の省力化、時にはバターの代わりに植物油脂を、牛乳の代わりに脱脂粉乳や水を用い、さらに殺菌工程も必要になります。これで本当にホワイトソースになるのかと、最初の頃はかなり戸惑いました。おいしいものを作りたいのに求められるものはそうではない、それが香料会社に入ったことなのだと自分の中で消化するには多少の時間は必要でした。
今ではフレーバリストやメーカーの方が望んでいるような基材を調製することに誇りをもっていますし、独自の提案もできるくらいのスキルを身に付けました。味が不完全な基材にフレーバーを加えて、まるでレストランの風味に仕上がったときには大きな達成感を感じます。そのフレーバーがメーカーに採用され、商品という形になったときには、感慨深いものがあります。レストランのシェフはお客さまと1対1の関係にありますが、香料会社として自分が関わった商品は広く日本中の消費者の方に飲食される可能性があります。これはホテルでは経験したことのないうれしさでした。
ホテルシェフの目指すところはそれをお出しするお客さまにおいしいと思っていただくことです。香料会社のコーポレートシェフの目指すところは着地点は違っても、同じことだと思います。フレーバリストの必要とする基材、メーカーがイメージする基材、それらが求められる到達点であり、そのためにある限りの力をふるうということについては料理人として大いにやりがいを感じます。
フレーバリストに本物の味を知ってもらう
若いフレーバリストたちに妥協のない料理の風味を知ってもらうことも、私の大切な仕事です。仕上がったものだけではなく、その過程を知ってほしいのです。料理は経時的に香りが変わってくる、そこに香りのポイントがあると思うからです。チキンブイヨンを例に挙げると、最初はハーブ、香味野菜、チキンの生臭さがバラバラにあるだけですが、3~4時間たつとそれらが一つにまとまります。また、肉を焼くときは、焼き始めの最初の香りから焼き上がったときの香り、その途中には刻々と変化する香りがあります。それらの中にメーカーが求めているいい香りがあるかもしれないからです。


新入社員の実地の研修を行うこともあります。その時はホワイトソースを題材に、一つは簡易基材、もう一つは本格的なソースという2種類を作ることとしています。まず、簡易的に作ったホワイトソース基材にフレーバーを加え、おいしくなった様子を見てもらいます。次に本格的なソースを作ります。バターを溶かしてプチプチと泡立ってきたら小麦粉を入れ、さらにかき混ぜて炒めていくと小麦粉の生臭さがなくなってクッキーのような香りに変化します。そこで牛乳を加えるとまた香りが変わり、乳の甘みも出てきます。調理の過程での香りの変化、素材そのもののうま味を感じてほしいのです。そしてフレーバーを加えておいしくなったホワイトソース、私が作った本格的なホワイトソース、それらの風味の違いを覚えてもらうことで、今後の彼らの業務に活かしてもらえるのだと信じています。
もう一つの例として、トリュフの香りの勉強会を行ったことがありました。本物のイタリアの白トリュフ、フランスの黒トリュフを取り寄せ、本格的なイタリア料理とフランス料理を作りました。その時は私も料理人としてだいぶテンションが上がりました。日本では本物のトリュフを食べる機会も知る機会も少ないし、食べ慣れないとそのおいしさを知ることもありません。若いフレーバリストも同じです。そんな彼らが私の作った料理からトリュフの香りを感じ取り、とても良いトリュフフレーバーを完成したことは、コーポレートシェフとしてだけではなく、料理人としても非常にうれしい経験でした。
料理人が幸せを感じるとき
「おいしい料理」を考えるとき、私が食べて幸せを感じる料理をまず思い浮かべてみます。それは故郷の山形の田舎料理、それもわが家の今は亡きおふくろの料理かもしれません。庭先の畑でとれた枝豆を「ずんだ」にしたり、キュウリやナスを山形の「だし 」にしたり、山形の郷土料理の芋煮はマストですが、それをベースにゼンマイやゴボウ、豆腐などを入れたわが家のお雑煮など。食べて、ほっとして、ああ帰ってきたなあ、と思えることが自分にとっておいしい、幸せの時間なのだと思います。前述したマンマの料理が一番おいしいと言ったイタリアンのシェフと同じです。そして、かなわぬことですが、母からもっと郷土料理を教わっておけばよかったとも思います。ただ、運よく妻も同郷の出身なので、芋煮や雑煮、山形の郷土料理を今でも食べられることに感謝しています。今、人生最後の晩餐は何を食べますか?と聞かれたら、もちろん芋煮と答えます。


私が好きな香りは、料理を作っているときの香りすべてです。チーズが焼ける、オマールエビをローストする香りなど。中でもやはりハーブ類が大好きです。バジルはイタリアンの勉強を始めた頃、タイムやローズマリーは本格フレンチレストランで修業をした頃の情景をよみがえらせます。それ以前の日本ではほとんどがドライハーブしかなく、本場のフランスのレストランで修業された大先輩たちが帰国されフレンチレストランが増えたことで、バジル、セルフィーユ、セージ、エストラゴンなどのフレッシュなハーブを使う機会を得たこと自体が幸せでした。
今の私は、このローズマリーを使うのだったらあの素材とあの素材をマリネして、ローズマリーでオイルに香りをつけてから焼いて、ソースの中に刻んでちょっと入れ、という手順と香りを想像するだけで、ああおいしい、幸せだなという気分になります。
やはり自分にとっての「おいしい料理」は容易にイメージできるものですね。
おいしい料理とは
「おいしい料理」とは……。いろいろ考えましたが考えれば考えるほど本当に答えが出ませんね。自己満足かもしれませんが、作り手の想いは必ず料理に反映されると思っています。
何も考えず、余計な理屈も能書きもなく、パクッと食べて「わあ、おいしい!」という言葉が思わず出たら、きっとその時の料理がその方にとっての「おいしい料理」ということに間違いはありません。そして、料理人はその言葉を聞きたくて日々奮闘しているのです。自分の作った料理で誰かにおいしいと感じてもらえる、こんな素敵なことはありません。もしかすると「おいしい料理」とは、料理人を一番幸せにする料理のことなのかもしれません。そしてその料理があなたをも幸せにしてくれる料理だったら……。
やっぱり、生まれ変わっても料理人になりたい、そして作りたいのは「おいしい料理」、心からそう思います。


- 石川 宏二 いしかわ こうじ
-
長谷川香料(株)総合研究所コーポレートシェフ
ホテルシェフとして30年以上勤めたのち、長谷川香料のコーポレートシェフとなる。総合研究所にてフレーバリストとともに基材の企画、開発に従事している。高い料理センスと幅広い知識、フレンドリーなキャラクターで一目置かれる存在。料理を作り始めると厳しい一面も…。
見出しのみを表示する